「小1の壁(しょういちのかべ)」という言葉をご存知でしょうか?
この言葉は、子どもが保育園・幼稚園を卒園し、小学校に入学するタイミングで、仕事と育児の両立が急に難しくなる状況を表す社会的な課題です。特に共働き世帯やひとり親家庭にとっては、子どもの入学は喜ばしい一方で、生活スタイルの大きな変化による戸惑いや困難が待ち受けています。
保育園時代には、朝早くから夕方遅くまでの延長保育が当たり前のように利用できていた家庭も、小学校入学後はそのペースが一変します。学校は早く終わり、学童保育も定員に限りがあり、保護者の就労時間と合わなくなることが多く発生します。
これは単なる生活の変化ではなく、働き続けたいと願う保護者にとっての深刻な壁なのです。
小1プロブレムとの違いとは?「子どもの問題」と「親の壁」
「小1の壁」とよく混同されがちな言葉に「小1プロブレム」というものがあります。この2つの違いを理解することは非常に重要です。
「小1の壁」は、親が直面する問題です。子どもが小学校に入ることで、保護者の働き方や生活スケジュールに影響が出る、いわば“親の壁”です。
一方、「小1プロブレム」は、子どもが直面する学校生活への適応の問題を指します。保育園や幼稚園では自由な活動が中心だった子どもたちが、小学校での45分授業や規則的な生活に慣れず、授業中に立ち歩いたり、集団行動ができなかったりする状態が問題視されています。
つまり、「小1の壁」は大人側の環境変化の問題であり、「小1プロブレム」は子ども側の適応課題という違いがあります。
小1の壁が起きる5つの代表的な原因
学童保育の時間が短く、預け先に困る
保育園では親の就業時間に合わせて柔軟に対応してくれる延長保育制度がありますが、小学校ではそのような制度が十分ではありません。学童保育も夕方には閉まってしまい、残業や通勤時間を考慮すると対応しきれないケースが多く見られます。
また、学童保育自体が定員制で、地域によっては希望しても入所できない場合もあります。2024年には、学童に入れなかった子どもが1万8000人を超えるなど、待機児童問題は依然として深刻です。
平日に増える学校行事や保護者の役割
小学校では、授業参観、個人面談、運動会、PTA活動など、保護者が学校に関わる機会が一気に増えます。これらのイベントは多くが平日に行われ、仕事を休まなければならない場面が増えてきます。
また、役員選出や行事の手伝いといったボランティア的な活動もあり、保護者としての負担は想像以上です。
学用品の管理や宿題のフォローで親の負担が増す
入学後は毎日の宿題の確認や提出物の管理、学校で必要な学用品の準備など、子どもに関する業務が一気に増えます。とくに1年生のうちは子どもがまだ自分で管理できないため、保護者がフォローしなければなりません。
ランドセルの中身チェック、プリントの確認、体操服や給食セットの準備など、細かなタスクが毎日続き、特に働く親にとってはストレスの元になります。
情報伝達が不十分になる小学校との距離感
保育園では連絡帳などを通じて、先生と保護者の間で毎日のようにやり取りがありました。しかし小学校では、そうした密なコミュニケーションは基本的にありません。
学校からのお知らせはプリントで渡され、それを子どもが持ち帰る形になるため、親が気づかないうちに提出期限が過ぎていた…ということも起こりがちです。
夏休みなどの長期休暇中に預け先がない
最大の小1の壁とも言えるのが、夏休みや冬休みなどの長期休暇中の預かり問題です。保育園と違い、小学校には「休暇保育」のような制度がありません。
学童保育が利用できればよいですが、定員オーバーで入れない場合や、長時間の預かりをしていない場合も多く、共働き家庭にとっては大きな悩みの種となります。
海外の教育制度と比較して見える日本の課題
例えばフランスでは、小学校の授業が朝8時半から夕方4時半まで行われ、さらにその後も「エチュード」と呼ばれる補習時間があり、午後6時頃まで子どもを預けることができます。
さらに、長期休暇中は「サントル・ド・ロワジール」という公的な学童保育施設が整備されており、レクリエーションや給食、遠足なども含まれていて、親の就労を妨げない体制が整っています。
こうした海外の事例と比べると、日本では保護者に求められる負担が多く、まだまだ育児と就労の両立を社会全体で支える体制にはなっていないことが明らかです。
政府と自治体の取り組みも少しずつ前進中
内閣府は2014年に「放課後子ども総合プラン」を打ち出し、学童保育の受け皿を拡充する政策を進めています。2018年にはさらに強化された「新・放課後子ども総合プラン」が策定され、学校施設内での学童運営の促進が進められています。
さらに、2024年からは「朝の小1の壁」対策として、一部の自治体で小学校での早朝預かりの取り組みが開始されました。これは、保育園では7時台からの預かりが可能だったのに対し、小学校では登校が8時以降であるため、通勤時間と合わないという問題に対応したものです。
小1の壁を乗り越えるためにできる家庭と企業の対策
保護者が取り組むべき工夫
-
子どもに自立を促す習慣づけ
洋服の準備、登校の支度、持ち物チェックなどを、少しずつ子ども自身に任せていくことで、親の負担を軽減することができます。 -
民間サービスの活用
民間の学童保育、子ども向けの習い事、ファミリーサポートセンターなど、公的支援が利用できない場合の代替策を検討しておきましょう。 -
保護者ネットワークを活用する
送迎の分担や情報共有ができる保護者のつながりをつくっておくことも、有効な対策のひとつです。
企業ができる取り組み
-
フレックスタイム制度やリモートワークの導入
柔軟な勤務体系を整えることで、小1の壁に直面する社員の離職を防ぎ、生産性の維持にもつながります。 -
社内コミュニティの形成
同じように子育てをしている社員同士の相談の場やサポート制度の共有は、働きやすい職場づくりの第一歩です。 -
マネジメント層の理解促進
上司や管理職が「小1の壁」に対して正しい理解を持ち、サポートの姿勢を示すことが、職場全体の雰囲気に大きく影響します。
まとめ:「小1の壁」は子育て社会に求められる変化の象徴
「小1の壁」は、子どもの成長とともに訪れる新たなライフステージであり、共働き家庭にとっては試練とも言える時期です。しかし、これは個人の努力だけで乗り越えられる問題ではありません。
政府の制度、企業の柔軟な姿勢、家庭内での工夫、地域との連携など、多方面からの支援があってこそ、「小1の壁」は乗り越えられるものです。
子どもの成長に寄り添いながら、社会全体で支え合える環境づくりを進めていくことが、これからの日本社会に求められる大きな課題だと言えるでしょう。




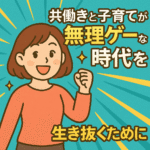


コメント